投稿日: 2023年12月20日 11:10 | 更新:2024年2月18日16:19

女性脳神経外科医として世界トップの手術件数を誇る藤田医科大学ばんたね病院 脳神経外科教授の加藤庸子医師。日本のみならず、世界中の医師に対して指導を重ねてきた。卓越した手技の研鑽に打ち込んできた時代と、後継者に技術を伝える今日について、話を伺った。
女性脳外科医のパイオニアとして技術の研鑽に励む
―― 診療科として脳神経外科を選ばれた理由を教えてください。
―― 当時の医局の雰囲気は。
できたばかりでしたから、最初は外来の患者さんも一日に5人とか10人くらいと少なかったですね。それがだんだんと100人、200人と増え、何より救急患者さんが、ものすごく多くなったことで、たくさんの手術件数を有する病院になっていきました。次から次へと患者さんが来て、一日が終わらない。佐野先生がご自分のジープで患者さんの家まで出向いて、救急車代わりで連れてくるなんてこともありました。
くも膜下出血や脳出血、脳梗塞などのさまざまな脳卒中の患者さんを治療する姿を見学する機会も多くありましたし、とても楽しく充実した日々でした。術後の管理をしていて、また今日も午前様になったとか、そんな感じで、それをよしとする時代だったし、そこに生きがいを感じているふたりの医師が、私のメンターでした。
20代から30代半ばまではそんな日々を送っていました。特に女性の脳神経外科医は数が少なかったので、自分の父親くらいの年齢の、いろいろな大学の主任教授たちは面白がって、「元気な子が入ってきたね」といった反応をされていました。同時に「いつまで辞めずに頑張るんだろうね」みたいな思いも、抱かれていたんだろうなとは感じていました。
くも膜下出血や脳出血、脳梗塞などのさまざまな脳卒中の患者さんを治療する姿を見学する機会も多くありましたし、とても楽しく充実した日々でした。術後の管理をしていて、また今日も午前様になったとか、そんな感じで、それをよしとする時代だったし、そこに生きがいを感じているふたりの医師が、私のメンターでした。
20代から30代半ばまではそんな日々を送っていました。特に女性の脳神経外科医は数が少なかったので、自分の父親くらいの年齢の、いろいろな大学の主任教授たちは面白がって、「元気な子が入ってきたね」といった反応をされていました。同時に「いつまで辞めずに頑張るんだろうね」みたいな思いも、抱かれていたんだろうなとは感じていました。

上の世代から受け継いだ手技を次世代に伝えていく
―― 開頭クリッピング術とはどのような手技なのでしょうか。
脳動脈瘤の患者さんに対して行われている手術です。頭を開いて瘤ができている脳の血管をクリップで挟み、破裂を防ぎます。クリップはいろんな形があって、動脈瘤の形、硬さ、向き。そういうものによって選ぶことができます。メーカーもたくさんありますし、全部合わせると200種類は超えています。動脈瘤の見極めができないと、クリップが閉まらないという事態になりかねないので、経験に基づいた選択が重要ですね。
脳神経外科には医局員が9人いて、医局長は病院准教授の山田康博先生が務めています。非常に信頼がおける医局長です。山田先生は私からクリッピング術を継承した、かなりのベテランですね。手技だけではなく、例えば大出血が起きたときに、どう止めるかといった、予定外のことが起こったときのレスキューの仕方も学んでくれています。
脳神経外科には医局員が9人いて、医局長は病院准教授の山田康博先生が務めています。非常に信頼がおける医局長です。山田先生は私からクリッピング術を継承した、かなりのベテランですね。手技だけではなく、例えば大出血が起きたときに、どう止めるかといった、予定外のことが起こったときのレスキューの仕方も学んでくれています。

クリップを症例ごとに選択する
(写真はミズホ株式会社製のクリップ)
時代の移り変わりに合わせたチーム医療の体制構築に尽力
―― どのような医局づくりを?
サブスペシャルティ(専門分野)はもちろんのこと、年齢、性別、国籍もばらばらのスタッフが集まっています。中には留学生もいます。何かあった場合は、医局員が山田先生に相談するようにしています。やっぱり、そういう役割を果たしてくれる人がいることが、教室が安定化するためには一番大事かなと思っています。チームの一体感の向上にもつながっていると思います。
自分が若い頃とは時代が違うから、若手は考え方も違いますね。だからこそ、できるだけ自由に、よほどのことでない限りはだめとは言わないようにして、自分の考え方やアイデアを活かしてもらっています。
私にも「こういうことがいいんじゃないですか」といろいろとアドバイスしてくれることがあるので、若い人たちの新しい意見も取り入れながらやっています。相乗効果ですね。
自分が若い頃とは時代が違うから、若手は考え方も違いますね。だからこそ、できるだけ自由に、よほどのことでない限りはだめとは言わないようにして、自分の考え方やアイデアを活かしてもらっています。
私にも「こういうことがいいんじゃないですか」といろいろとアドバイスしてくれることがあるので、若い人たちの新しい意見も取り入れながらやっています。相乗効果ですね。
―― 働き方も変化している?
2024年からは医師の働き方改革で、労働時間の制約が厳しくなります。今まで通り患者さんをたくさん診ながらも、働き方のバランスを重視する必要があります。当科では手術の数や検査の数を考慮したうえで、一週間に一日、ノー残業デーを設けるようにしています。ただ、働き方改革といっても医師の数が急に増えるわけではないので、多職種とのタスクシフトやタスクシェアが重要になります。そこで活躍するのは診療看護師。実務経験を経て大学院を修了した、医師と看護師の間の仕事ができる存在で、例えば手術助手を務める、血糖値のインスリン投与量や人工呼吸器のコントロールを担当するなど、以前だったら医師がすべて実施していた医療行為の一部を、看護師たちが医師の指示の下にやってくれています。当科にも専属の診療看護師が在籍しています。
「加藤先生が診てくれる」患者の信頼が元気の源
―― コロナ禍による変化は。
脳神経外科に関しては、患者さんの受診控えや手術数の減少などはあまりありません。ただ、コロナに罹った患者さんから話を聞いていると、心に傷を負い、自信をなくしてしまっている印象は受けました。気持ちが沈んでいるんですね。だからそういった心の面が、病気に影響しないようにということは考えていました。病気だけを治すのではなく、全人的に診る必要があるな、と。
そうはいっても、私の方が患者さんから元気をもらうこともあります。もちろん自分が健康でないと、相手にも健康になってはもらえないでしょう。患者さんたちは医師が病気になるとは思っていません。医師はいつも元気だと思ってくださる気持ちが、私を守ってくれていると感じています。患者さんからの信頼に応える形で、私自身も健康でいられます。
週末には病棟で患者さんとラジオ体操をしています。コロナ禍だから3メートル間隔を空けるようにして、交流と体力づくりを行っています。患者さんも人とのつながりができたり、運動が昨日よりもできるようになったりと、お互いに高め合うことになります。集団で何かをやるのはいいことですね。
また、コロナ禍で人数が減りましたが、もともと留学生をたくさん招聘していました。現在もインドからひとり来ていて、間もなく次々に来る予定です。留学生の中にいるだけでも英語の会話が始まったり、英語で論文を書いたりと、海外に目を向けたアクションが教室の中に生まれます。国際交流はとても大事だし、英語を使えることも重要です。日本の医師たちも海外へ行ってもらえればと思います。
そうはいっても、私の方が患者さんから元気をもらうこともあります。もちろん自分が健康でないと、相手にも健康になってはもらえないでしょう。患者さんたちは医師が病気になるとは思っていません。医師はいつも元気だと思ってくださる気持ちが、私を守ってくれていると感じています。患者さんからの信頼に応える形で、私自身も健康でいられます。
週末には病棟で患者さんとラジオ体操をしています。コロナ禍だから3メートル間隔を空けるようにして、交流と体力づくりを行っています。患者さんも人とのつながりができたり、運動が昨日よりもできるようになったりと、お互いに高め合うことになります。集団で何かをやるのはいいことですね。
また、コロナ禍で人数が減りましたが、もともと留学生をたくさん招聘していました。現在もインドからひとり来ていて、間もなく次々に来る予定です。留学生の中にいるだけでも英語の会話が始まったり、英語で論文を書いたりと、海外に目を向けたアクションが教室の中に生まれます。国際交流はとても大事だし、英語を使えることも重要です。日本の医師たちも海外へ行ってもらえればと思います。
※『名医のいる病院2023』(2023年1月発行)から転載



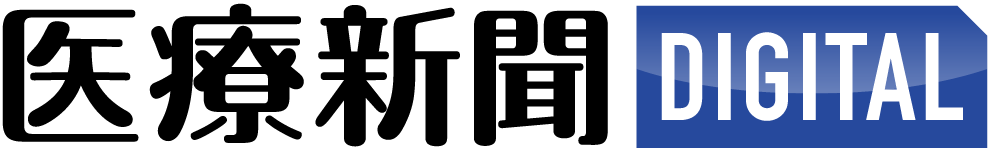













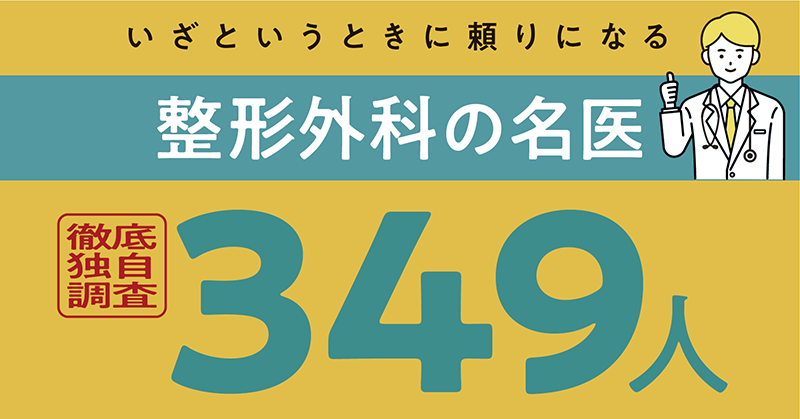




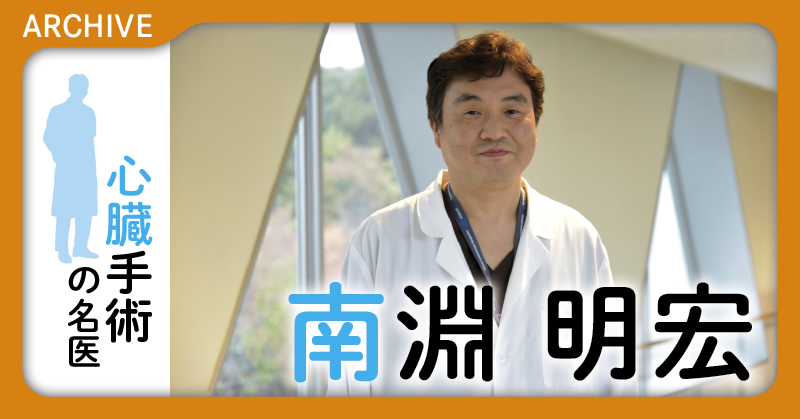



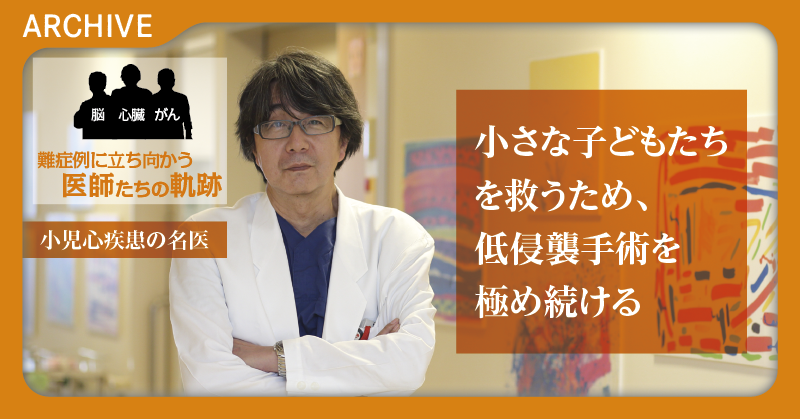


















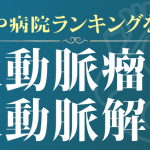


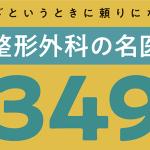







卒業後は名古屋保健衛生大学(現在の藤田医科大学)の脳神経外科に入局し、医局の二代目教授を務めていた神野哲夫先生と、クリッピング術の名医である佐野公俊先生から、手とり足とり、顕微鏡を使った手術について教えていただきました。