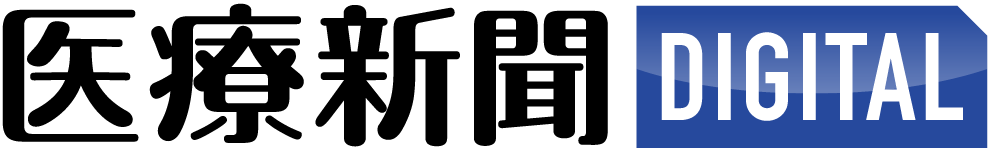白血病防ぐ遺伝子発見 金大研究グループ 治療法確立に期待
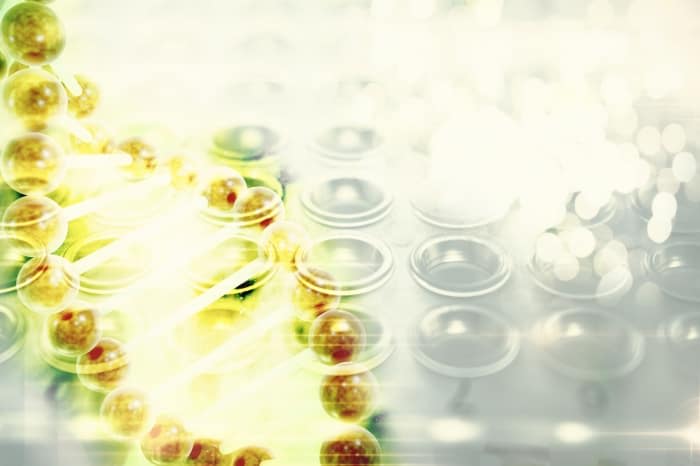
理研、ゲノム解析で日本人特有の遺伝的変異を解明 飲酒量や血糖値等に関係
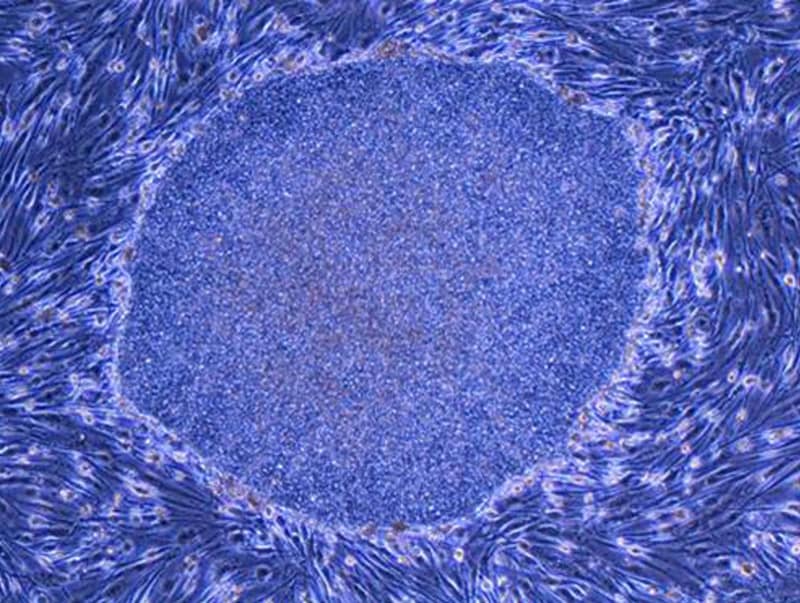
iPS創薬で難聴治療の候補物質

敗血症は特定タンパク質増で改善

新たにがん3種の適用申請
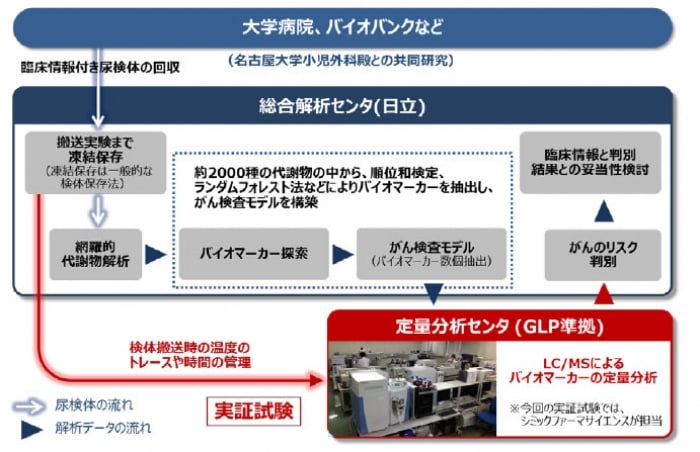
尿による簡便ながん検査に向け日立が実証試験を開始

不安対処し心に健康を 日本予防医療ネットワーク 大阪でイベント
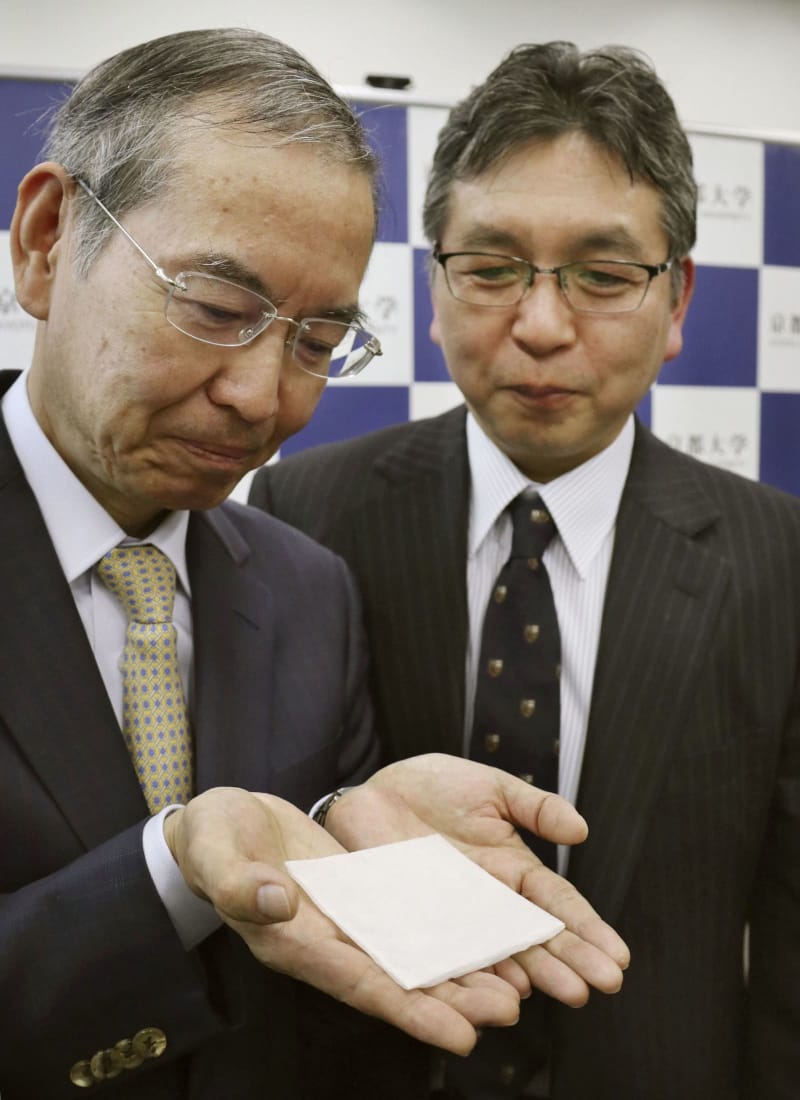
血管成長促し皮膚修復、京大開発

脳脊髄液漏れ高精度診断 福島医大が新手法発見、タンパク質に注目

小児がんを尿検査で判別、日立

世界初の入浴介護ロボを開発 富大、年度内に試作機

心不全の診断 血液検査で有力な指標

理研が京都にiPS創薬拠点
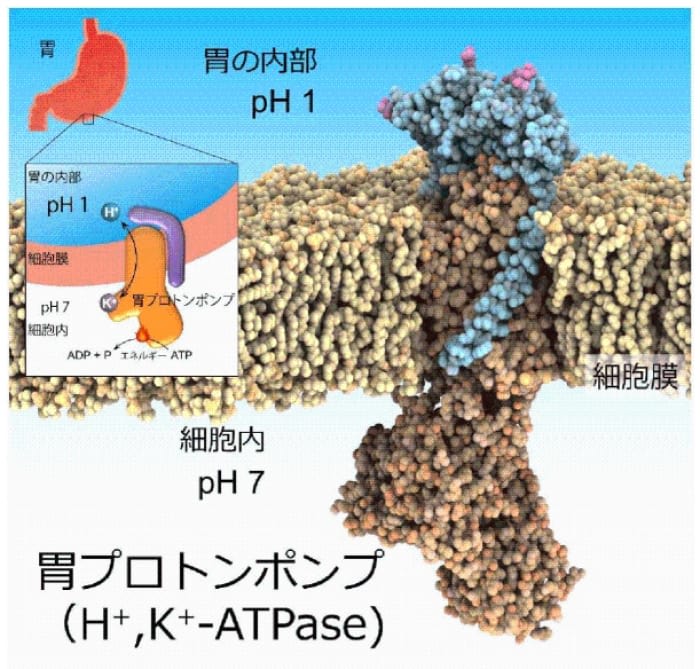
胃プロトンポンプの構造を原子レベルで解明、名古屋大学の研究
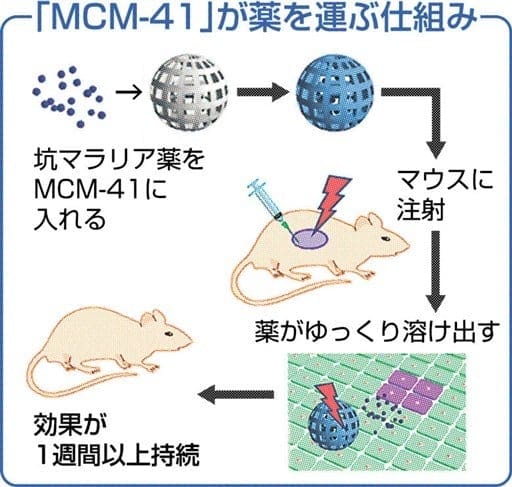
効き目長いマラリア薬開発へ 熊本大グループ 薬代の抑制も

脳卒中のリハビリ促進薬を発見

ラベンダーとティーツリー、思春期前の男児に悪影響を与える可能性
コーヒー発がん性警告を

iPSと人工知能で創薬、京大
- 毎月アーカイブ
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- カテゴリーアーカイブ